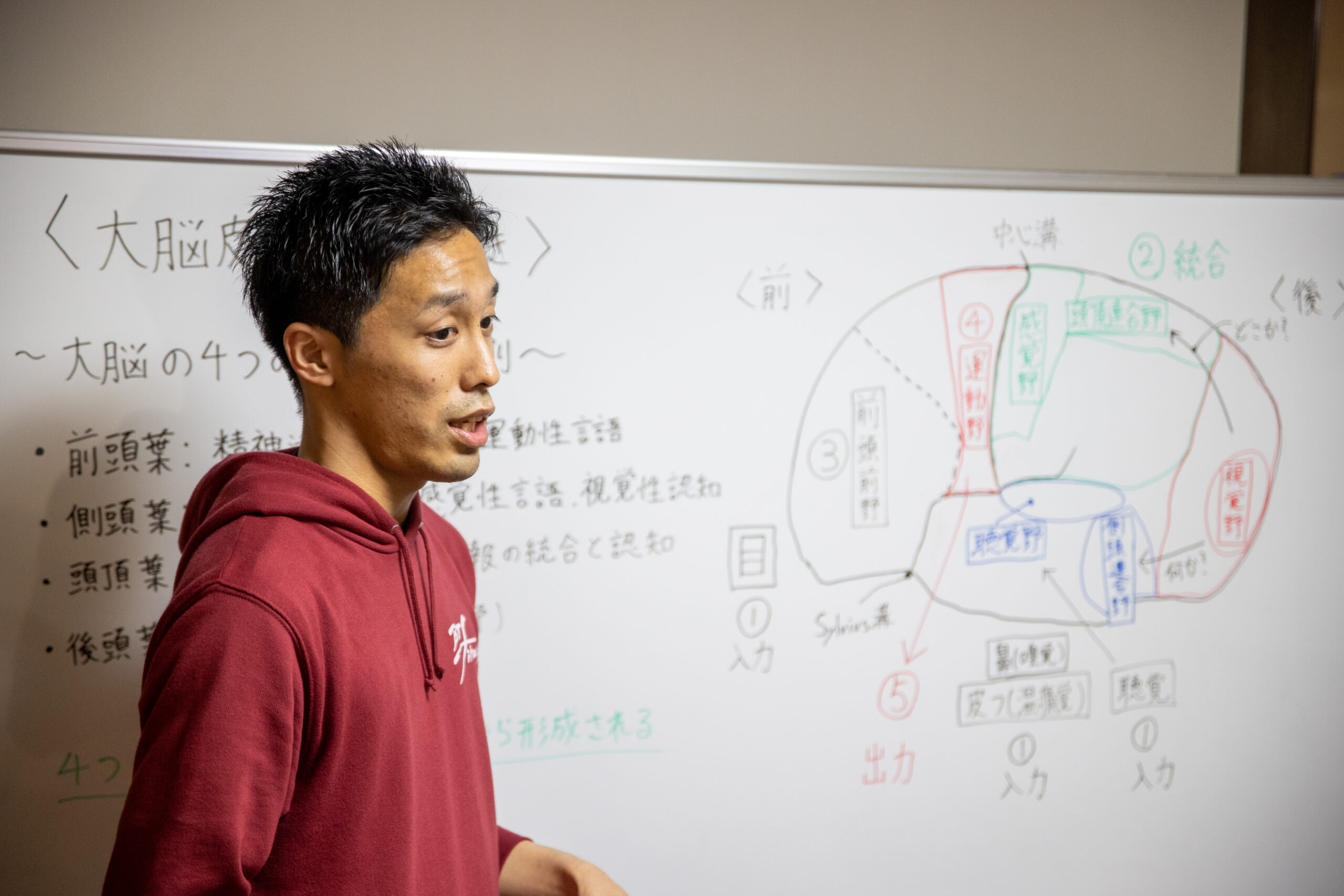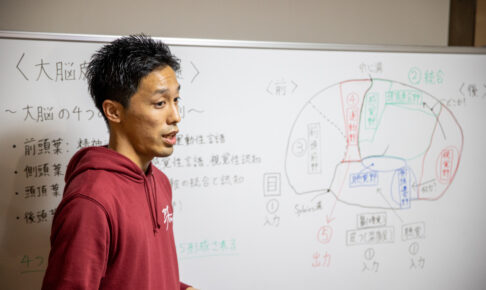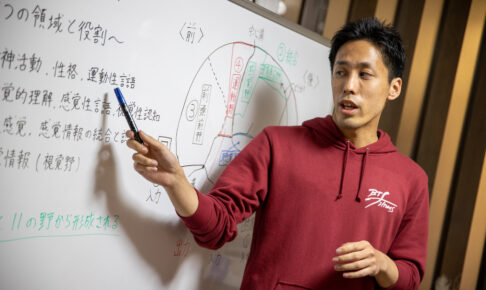運動時の糖代謝は、身体が活動に必要なエネルギーを得るために、糖質(主にグルコース)をどのように利用するかというプロセスを指します。以下では、その基礎的な仕組みから、無酸素・有酸素運動での違い、運動強度や時間による代謝の変化について解説します。
糖代謝の基本:グルコースがエネルギーに変わる流れ
糖質の摂取と消化吸収
食事から摂取した糖質(ご飯、パン、果物など)は、小腸でブドウ糖(グルコース)に分解され、血液中に吸収されます。
血中グルコースの運搬
血中のグルコースはインスリンの作用により、筋肉や肝臓に取り込まれます。余ったグルコースはグリコーゲンとして肝臓や筋に蓄えられます。
ATP生成の流れ
運動中、グルコースは細胞内で以下の順に分解され、ATP(エネルギー通貨)が作られます:
解糖系(細胞質)
クエン酸回路(ミトコンドリア内)
電子伝達系(ミトコンドリア内)
運動の種類で異なる糖代謝
●無酸素運動(高強度・短時間)
主な代謝経路:解糖系
特徴:
酸素を使わず、グルコースをピルビン酸→乳酸へと変換しながらATPを生成
素早くエネルギーを供給できるが、効率は悪く、乳酸蓄積により疲労を招きやすい
例:スプリント、ウエイトトレーニング、HIIT
●有酸素運動(中〜低強度・長時間)
主な代謝経路:解糖系 → クエン酸回路 → 電子伝達系
特徴:
酸素を用いてグルコースや脂肪を完全に酸化し、多量のATPを生成
持久的な運動に向く
例:ジョギング、ウォーキング、長時間の自転車走行
運動とグリコーゲンの関係
筋グリコーゲン:高強度運動時の主要エネルギー源。枯渇するとパフォーマンスが著しく低下。
肝グリコーゲン:血糖を維持するために使われ、特に長時間の運動で重要。
運動後の糖代謝と超回復
運動後の筋はグルコース取り込みが亢進:インスリン感受性が高まり、筋グリコーゲンの再合成が促進される。
摂取タイミングが鍵:運動直後〜2時間以内に炭水化物を摂取することで、グリコーゲンのリカバリー効率が高まる。
糖代謝と持久力トレーニングの適応
ミトコンドリアの増加:糖と脂肪の酸化能力が向上
グリコーゲンの貯蔵量アップ
乳酸処理能力の向上:解糖系代謝産物である乳酸を効率的に代謝できるようになる
糖質制限下での運動パフォーマンスは?
低糖質・ケトン食は持久的運動には適応可能だが、高強度では糖が必要不可欠
高強度では糖なしではパフォーマンスが著しく低下する(Bergstromらの筋生検研究より)
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。